現在、新型コロナウイルスのパンデミックによって、国内外の社会は激しく動揺し、刻々と変化する状況とそれを伝える情報の洪水に、私たちの生活は振り回され、変容を強いられています。いま私たちがなすべきはまず第一に、科学的に正しい情報に従い、感染拡大防止に努めることでしょう。しかし同時に、この「非常事態」が何を意味するのか、慌ただしい状況の中で、少しだけ立ち止まって考えることも必要ではないか、と私たちは考えます。時間的・空間的なスパンを長くとって、物事を掘り下げて考えようとする人文社会科学の立場から、京都大学・人社未来形発信ユニットは、みなさんに立ち止まって考えていただくきっかけを提供したいと考え、対談インタビューシリーズを企画しました。タイトルは
「立ち止まって、考える―パンデミック状況下での人文社会科学からの発信」
です。
今回から週2回のペースで公開されるシリーズの第1, 2回は、人文科学研究所・藤原辰史准教授と、本ユニット長・出口康夫教授の対談を前後編に分けてお送りいたします。この対談は2020年4月2日に行われました。(以下の対談ダイジェスト動画もご覧ください。)
出口康夫 (人社未来形発信ユニット・ユニット長、以下出口) 現在、新型コロナウイルスのパンデミックという状況の下、国内外が激動し、人類全体が大きな試練に晒されています。また情勢が日々刻々と変わる中、さまざまな情報が乱れ飛び、われわれとしても心が浮き足立ち、個人的にも社会としても大きく動揺しています。一方、人文知・社会知は、生命や社会を守ることには直接貢献できないにしても、目の前の出来事を時間的・空間的なスパンを長くとって見る、ないしは原理的に掘り下げて深く考えるという姿勢を貫いてきました。そこで、京都大学の人社未来形発信ユニットとしては、そういった人文社会知の立場から、皆さんに立ち止まって考えていただくきっかけとなるような話題を提供したいという意図の下、コロナ・パンデミックをめぐる対談インタビューシリーズを企画し、その第一回として、現代史がご専門の京都大学人文科学研究所の藤原辰史さんにお越し頂きました。藤原さん、よろしくお願いいたします。
藤原辰史 (人文科学研究所・准教授、以下藤原) よろしくお願いします。
スパニッシュ・インフルエンザとの類似点、相違点
出口 人類は過去、今回のコロナ・パンデミックのような伝染病・疫病の流行を何度も経験してきましたが、藤原さんのご専門の現代史の範囲では、スペイン風邪が有名なケースだと思います。その事例と重ねながら、現状をどうお考えなのか、まずはそのあたりからお聞きしたいと思います。
藤原 私は、スペイン風邪の専門家ではないのですが、20世紀において一番大きなパンデミック、「スペイン風邪」と日本語では訳されていますけれども、スパニッシュ・インフルエンザについて今知ることがとても重要だと考えています。
まず、私がどうして、スパニッシュ・インフルエンザというテーマにあたったかといいますと、人文科学研究所で8年間ほど第一次世界大戦の総合的研究という共同研究をしておりまして、その成果として、人文書院から「レクチャー 第一次世界大戦を考える」(12冊)、岩波書店から『現代の起点 第一次世界大戦(全4巻)』を刊行しましたが、第一次世界大戦の研究の最後の年、1918年からアメリカ発のインフルエンザが世界中に蔓延していったという事例についても幾度か議論になり、私も調べました。統計によりますと、4000万人から1億人ほどの人がスパニッシュ・インフルエンザによって亡くなったといわれているぐらい、大規模な悲劇があったのです。第一次世界大戦の資料を探していますと、どうしてもスパニッシュ・インフルエンザの資料がいっぱい出てきますから、それを読んだり、写真を見たりして、いろいろ考えることがありました。その特徴を、今の新型コロナウイルスの状況と比べますと、いくつか類似点があると思いますね。

一つ目、一番重要な類似点は、スパニッシュ・インフルエンザのときも今も、人の移動が非常に激しかったということです。スパニッシュ・インフルエンザのときには、第一次世界大戦という世界のあらゆる国が戦争のかかわってくる大戦争をしていました。そのときにアメリカが参戦して、アメリカからどんどんヨーロッパ大陸に大きな輸送船が若い兵士たちを積み込んで大陸に上陸していくという、そういうことが繰り返されたわけですが、まず船でクラスターが発生します。換気が悪く、密度の濃い大きな船の中で、若い兵隊さんたちが感染して亡くなっていくという事例がありました。兵士が移動するだけではありません。当時は労働力も不足していましたから、たくさん中国から「クーリー」がヨーロッパに上陸して、労働力として雇われていたり、それからイギリスやフランスは東南アジアに植民地を持っていますから、その植民地からも兵士とか、あるいは労働力としてたくさんの人がヨーロッパに行っていたりしましたので、その人たちの移動の激しさというのが、このスパニッシュ・インフルエンザの世界的拡大をもたらしました。では、いまはどうなのか。百年前の戦争は、今のオーバー・ツーリズムですね。膨大な数の人が次々に、飛行機でも本当に分刻みでどんどん飛行機が下りていく、世界各国の人々が世界各地で旅行して帰っていくという状況ですね。今は見る影もありませんが。その人の移動という意味では戦争と観光という、あるいは仕事やわれわれのような学術の仕事も当然ありますけれども、その人の往来の激しさという意味では100年前といえども、とても状況は似ていると思います。
二つ目は、初動の誤りですね。初動の遅れという意味でも今の新型コロナウイルスとスペイン風邪って似ているところが多い。最初は皆さん楽観していました。政府で二月に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部の会合では、首相は八分間のみの参加で、大変重要な役職である環境大臣はなんと欠席していました。メディアもまだのんびりしていました。オリンピックという大きなイベントが七月に控えていたことも関係あるかもしれません。他方で、百年前の初動の後れは、戦争中だったことと関係します。戦争中で、軍人たちの敵は病気ではなくまず敵国であり、勝つという大きな目標があって、頑張ろうとするのですよね。多少調子が悪くても、上からの命令は絶対ですし、軍隊は裁判所ではなく、より厳しい軍法会議で裁かれますから、異議申し立てもしづらく、やはり少し調子が悪くても頑張ってしまいます。それがかえっていろいろな人にインフルエンザのウイルスを蔓延させていくきっかけになってしまう。そういうわけで、スペイン風邪のときにも、そこから最初の、例えば隔離とか、それから情報をみんなに伝えるとかいろいろなやるべきことあったはずですが、大きな出来事があると、そういうところで、最初の段階で油断してしまうことになります。簡単には止められないイベントや仕事や国際交流や経済活動があって、非常に深刻になってしまった今の状況とスパニッシュ・インフルエンザは似ていると思います。ですから、当時も今もですが、なかなか今までの自分の、自分たちの経験では対応できなくって、右往左往する中でどんどんと広まっているということですね。これが2点目だと思います。
出口 スパニッシュ・インフルエンザと今回のコロナ・パンデミックの似ている点を二つご指摘いただきました。次は、両者の違っている点ないしは今回のケースの新しい点についてもお話をお願いします。
藤原 ずれている点、違う点と考えるときに、「違うのだけれども実は似ている」点もあったりして、うまくきれいに分けることはできないかもしれませんけど、一つは情報ですね。やはり、今の社会は次々に新型コロナウイルスでどういう問題が起こっているのか、どういう症状なのか、何が問題なのかということが、SNSを通じて、インターネットを通じて、新聞、テレビ、雑誌を通じて、膨大な情報が流されていて、それが時々刻々と変わり、その情報のうち、非常に多くの情報が役に立たない、あるいは情報として知ってもあまり意味のないものであったり、あるいは大変重要な情報なのに全然伝わっていなかったりということがあります。絶対必要な情報量も、全然必要ではない情報量も、さらに言うと、変な言い方ですが、こんな情報があってはいけない情報といいましょうか、フェイクニュースのようなかたちで人の不安をあおるだけの、トイレットペーパー不足にも見られましたけれども、そういう情報の量がけた違いに存在するのが、今回の新しい点で、SNSの情報や小さなコミュニティの情報とかが錯綜する中で、個人個人も右往左往している。その意味では、第一次世界大戦のときはインターネットも、テレビも、ラジオもないですから、情報量は今と比べると少なかった。
ただし、第一次世界大戦のときには、既に海底ケーブルで各国がつながっておりまして、電信でかなりほぼ時差なく情報がリアルタイムでやり取りされる。そういう意味では、既に「世界性」、これは私たちの共同研究のキーワードの一つですが、それはもう生まれていたときでした。ですから、日本でもブラジルやアルゼンチンで起こっていることをすぐタイムリーに知ることができましたし、そういう意味で今の原型のような、情報のグローバリズムというのは第一次世界大戦期に存在していたと思います。
ただ、スペイン風邪という名前に見られるように、やはり当時の情報というのは限られていたと。なぜかというと、戦争中ですから、絶対に国内の、特に敵国に対して情報を漏らしてはいけないですよね。漏らしてはいけないということはどういうことかというと、メディアを制限するわけです。制限するとどうなるかというと、中立国の情報と交戦国の情報とで、情報格差が生まれて、中立国はインフルエンザが大変だとなったら、すぐ国際社会に訴えますけど、対戦国同士では、できるだけそういう弱いところを隠したいので、情報を流さない。当時中立国だったスペインはあらかじめできるだけ早くインフルエンザの情報を流しましたから、スパニッシュ・インフルエンザという名前が生まれました。日本語だとスペイン風邪と名前が変わっています。情報が限られることによって、決してスペイン発祥ではないにもかかわらずそう名前が変わってしまう。それは情報が統制されるがゆえの問題といいましょうか、間違ったネーミングというのが、そう生まれてきている。ただ、あとで出口さんからもぜひ意見聞きたいと思っているのは、しかし、今は情報社会になったのできっちり情報が伝わっているかというと、決してそうではない状況も見られていて、各政府がちゃんと情報を出して、その情報をもとに検討してやっているかというと、それもやっぱり国同士で全然温度差が違うような気がしています。だから、そういう意味で情報という点からすると、違う点もあれば似ている点もあって、今、そこをきっちり見ていく必要があると思います。
リスボン大地震
出口 では私のほうからも、いくつか問題提起をさせていただきたいと思います。既にお話しいただいた点にも絡むのですが、大きな災害が世界規模で起こる、ないしは局所的な災害だったとしても、その影響が世界の広い範囲に及ぶという事態は、世界史の中でも何度も起こってきたと思います。近代に限っても、18世紀の半ば、1755年に起こったリスボン大地震のケースが挙げられます。これは、東日本大震災と同様の、大津波を伴う海溝型地震で、ポルトガルの首都リスボンをはじめ、イベリア半島や北アフリカの西海岸の各都市を壊滅させた大震災です。この震災はまた、最初の「近代的災害」だとも言われています。その一つの理由は、震災に関する情報が、ヨーロッパで、またたく間に広く共有されたという点にあります。当時既にヨーロッパ各都市で新聞が発行され始めていて、リアルタイムとまではいかないにしても、数日ないし数週間以内にマドリッドやパリやロンドンなどのヨーロッパの主要都市に、地震とその被害状況についての情報が広まっていきました。中には、絵入りの報道も数多くありました。
藤原 絵があって、というのは大事ですよね。

出口 結果として、ヨーロッパ全体が同時代的に震災を経験したとも言える状況が生じました。この共有経験をベースとして、リスボン大震災は、ヨーロッパの思想史にも大きなインパクトを与えることになります。当時すでに、思想上の聖俗革命、すなわち、あらゆる価値の基準を神から人間へと置き換えていくというムーブメントが起こっており、そのラディカルなバージョンとして、神の存在や摂理を疑う無神論的な哲学もじょじょに登場し始めていました。そのような流れの中で、無神論のシンパたちが、無辜の人々が多数犠牲となった震災を、神の不在の証拠、ないしは神の存在に対する反証として持ち出したわけです。例えばヴォルテールは『カンディード』という作品の中で、リスボン大地震に言及し、善なる神が創造した以上、この世界は最善であるはずだとするライプニッツの最善世界説を皮肉るようなストーリーを展開しています。また地震の報道に接した幼いゲーテは、神の存在に深い疑念を抱く体験をしました。また若きカントは、リスボン地震に反応して、地震の原因を、神の摂理であるとか天罰としてではなく、神を排除する仕方で純粋に自然科学的に説明する試みも行ないました。ちなみにカントの説明は、当時すでにあった、地震の原因を地下の可燃物の爆発に求める説に、若干、手を加えたものに過ぎませんが。このように多くの人が報道を通じて共通経験を持つことで、リスボン大震災は、ヨーロッパの思想が神から離脱する動きを、一から生み出したというより、一歩、後押しする役割を果たしたわけです。同じことは、近現代日本が経験した大震災、例えば関東大震災や「3.11」についても言えると思います。ともに日本の社会のみならず、思想界にたいしても少なからぬ影響を与えました。では、スパニッシュ・インフルエンザの場合はどうだったのか、またそれを踏まえて、今回のコロナ・パンデミックのケースには、どのような可能性ないし問題点が考えられるのかをお聞きしたいと思います。
忘れられたパンデミック
藤原 今のリスボン地震のお話を聞きながら考えていたのは、このスパニッシュ・インフルエンザは、恐らく第一次世界大戦という違った災いと重なったせいで、ある意味このパンデミックというものが持っている独自性、そこから、あるいは思想的、新しい展開とか、あるいは何か衝撃を与えるようなものが少なかったと思いますね。そこがリスボン大地震と少し違うのかもしれません。
といいますのも、むしろ第一次世界大戦とスパニッシュ・インフルエンザを一緒にして考えるのであれば、これだけの非戦闘員の方が戦争中に、戦争していないのに亡くなったというのは初めてです。つまり、非戦闘員にとっても過酷だったという戦争の様相は、戦争によってかき回された病原菌やウイルス、そして、私の研究テーマの一つは飢餓ですが、戦争によってイギリスが中立国からの食料をドイツに行き渡らせないように船で封鎖し、それでドイツで76万人の餓死者が生まれたという悲劇に端的に現れています。ですから、第一次世界大戦のことを、「食糧戦争 (food war)」という研究者もいますし、私もそう考えています。新型コロナウイルスでも、食糧の在庫の偏りによって各国で飢餓が発生しやすい状況になるでしょう。すでにそういう事例も報道されています。私の研究も、栄養失調で体が弱ったところに病気が襲いかかるということも含めて、戦争というのは戦場だけで起こっているのではなくて、日常の世界で、普通にご飯を食べるということができなくなったり、普通に子どもたちを育てることができなくなったり、普通に子どもを産むことができなくなるという悲劇の様相を考えてきました。日常の延長としての戦争ですね。さらに、戦場でも兵士たちには、顔を洗ったり、髭を剃ったり、ご飯を食べたり、睡眠をとったり、トランプをしたり、手紙を書いたり、お祈りをしたり、という日常がありました。そこで第一次世界大戦のインパクトというのは、日常と戦争の境界が揺らいだことが大きいと思います。それにスパニッシュ・インフルエンザを含めますと、昨日まで当たり前だと思っていたことが、すぐに次の日にはもう消えてしまうという、無神論者よりももっとラディカルに、世界というのは一体であるのかどうか、福岡伸一さんのご著書にあるように生物と無生物の違いは何なのか、そもそも調和とか平和とかありえるのか、理性など野蛮の前に吹き飛ばされる塵芥ではないのか、そういうふうに、さまざまな今までの常識ががらがらと崩れていく、その一端を多分スペイン風邪というのは担っていることは間違いないと思います。
ただ問題なのは、スペイン風邪というのは、結局記憶としてはあまり残っていないのですよね。その研究者も第一次世界大戦と比べると少ないです。テーマが文系と理系にまたがるという理由もあるでしょう。亡くなった数からすると膨大ですが、歴史の教科書ではほとんど重視されていません。私は、環境史というジャンルにも足を突っ込んでいますが、環境史は文系と理系を架橋する学問分野で、パンデミックを考える際に役立つ知見を与えてくれます。アルフレッド・W・クロスビーという環境史家がスパニッシュ・インフルエンザについての本『史上最悪のインフルエンザ』(原典は1989年、翻訳は2004年)を執筆していて、みすず書房から翻訳されています(翻訳者=西村秀一)。私は彼の別の本『ヨーロッパの帝国主義――生態学的視点から歴史を見る』(佐々木昭夫訳、ちくま学芸文庫、2017年)で展開された「生態学的帝国主義ecological imperialism」という概念に興味があり、『稲の大東亜共栄圏』(吉川弘文館、2012年)で批判的に応用したことがあったので彼にはずっと関心を抱いていました。ベストセラーとなったジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(倉骨彰訳、草思社文庫、2012)でかなり参考にされた本でもあります。そのクロスビーの『史上最悪のインフルエンザ』を読みますと、何でこれほどまでに大事なことが忘れ去られたのか。これは、私たちが新型コロナウイルス後をどう考えていくかというときに、極めて重要なことだと思います。日本の研究者ですと、速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ——人類とウイルスの第一次世界戦争』(藤原書店、2006)も、日本での「スペイン風邪」の実態を明らかにしたとても貴重な歴史書ですし、山本太郎『感染症と文明—共生への道』(岩波新書、2011)はとても見通しのいい歴史書ですし、さらに飯島渉『感染症の中国史』(中公新書、2009)も学ぶべきことが多いです。つまり、歴史を学ぶことで、情報をちゃんと残して、どういうことが考えられたかも残して、いったい何が問題だったかということを、赤裸々に叙述して、しっかり分析していく必要があると思います。
その中でも第一次大戦のあとのスペイン風邪の歴史の中で、一つ重要な、残っている教訓みたいなものがあるとすれば、例えば小説とか、あるいは研究のなかに出てきているのは、こういうパンデミックが起こったときには、必ず今まで社会的に弱い立場にあった人にしわ寄せがくる、ということ。一つは貧困者ですね。クロスビーはこう述べています。「多くの家庭、とりわけスラムに暮らす家庭では、食事を作るだけの体力が残っている大人が誰もおらず、一家の稼ぎ手が寝込んでしまったり亡くなったりしてしまったために、食べ物がまったくないという状態に陥っているケースがいくつかあった」(p.105)。それから看護師さんですね。看護師さん、医療従事者の方は英雄的というべき仕事をこなしてきました。その中で生き延びた人たちの手記の中には、本当に看護師さんの献身的な支えで私は何とか生き残れた、というものがあります。彼女たちは、スペイン風邪が落ち着いたあとほとんど顕彰されていないし、いったい彼女たちがどういう戦いをしたのかということを、誰も注目しなかったわけです。戦争にかき消されてしまった。つまり、誰にしわ寄せがきているのかということを、私たちはちゃんと、新型コロナウイルスの前、今、そしてあとというかたちで凝視していく必要があると思いますよね。
(以下、後編に続きます。)
他のレポートを読む
-
report 2021/07/30
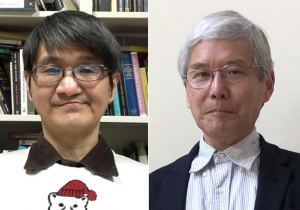
【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 科学哲学
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 仏教学・チベット学・ブータン学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 美学・芸術学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 現代社会論・社会思想 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える



 人社未来形発信ユニット基金
人社未来形発信ユニット基金