現在、新型コロナウイルスのパンデミックによって、国内外の社会は激しく動揺し、刻々と変化する状況とそれを伝える情報の洪水に、私たちの生活は振り回され、変容を強いられています。いま私たちがなすべきはまず第一に、科学的に正しい情報に従い、感染拡大防止に努めることでしょう。しかし同時に、この「非常事態」が何を意味するのか、慌ただしい状況の中で、少しだけ立ち止まって考えることも必要ではないか、と私たちは考えます。時間的・空間的なスパンを長くとって、物事を掘り下げて考えようとする人文社会科学の立場から、京都大学・人社未来形発信ユニットは、みなさんに立ち止まって考えていただくきっかけを提供したいと考え、対談インタビューシリーズを企画しました。タイトルは
立ち止まって、考える―パンデミック状況下での人文社会科学からの発信
です。
シリーズ第2回は前回に引き続き、人文科学研究所・藤原辰史准教授と、本ユニット長・出口康夫教授の対談後編をお送りいたします。(第1回・前編はこちらから、以下のダイジェスト動画もご覧ください)。なお、この対談は2020年4月2日に行われました。
出口康夫 (人社未来形発信ユニット・ユニット長、以下出口) スパニッシュ・インフルエンザと第一次大戦という二つの災厄が重なることで、ヨーロッパが、そして世界が、膨大な数の死者ないし死を、同時に共に体験し、それとともに当たり前と思われていた日常生活が音を立てて崩壊するという、これまた共通体験を持ったということですね。そのことと、その時期の哲学の流れの転換を結びつけるとすると、一つのキーワードはやはりニヒリズム、虚無主義になると思います。単なる無神論を超えて、すべての価値を否定し、その無根拠性を暴く思想としてのニヒリズム、キリスト教的な価値に代わる、人権や自由といった世俗的で啓蒙主義的な価値にも実は底がない、根拠がないとする徹底した思想としてのニヒリズムが本格的に流行り出し、ニーチェの著作が広く読まれ出すのが、ちょうどその時期に当たります。これは当時の日本も含めた全世界的な傾向です。そのニヒリズムが表面化、顕在化する一つの切っ掛けが、スペイン風邪と第一次大戦という二重の世界的災厄だと言えると思います。さらにこのニヒリズムの登場と連動する、哲学上の変化をもう一つ挙げさせていただきたいと思います。人々が世界大戦とパンデミックによる二重の大量死の経験をする以前の哲学の一つのキーワードは、「レーベン (Leben)」すなわち「生 (せい)」でした。
「生の哲学 (Lebensphilosophie)」という思想が、19世紀から20世紀初頭のヨーロッパでは一つの大きな流れになっていました。それが、二重の大量死の後、特にハイデガーが「生」というキーワードを、「トート (Tod)」つまり「死」という真逆のキーワードによって、いわば「上書き」したことによって、がらりと調子が変わることになります。生の哲学では、「生」が持つ「生き生きとした」(レベンディッヒ (Lebendig))な感じにハイライトが当てられていたのに対し、ハイデガーの『存在と時間』の一つの殺し文句は「覚悟せる実存の沈黙」です。ここでは、自らの死と直面し、鉛を飲み込んだように沈黙する自己という重苦しいイメージが前景化されています。ポジティブな「生」から、それをちょうど裏返したネガティブな「死」へと、大量死の時代を経て、哲学の基調が真逆に転換したわけです。
信頼すべきものの崩壊
藤原辰史 (人文科学研究所・准教授、以下藤原) なるほど。だから多分、今のハイデガーのお話をお聞きしながら感じていたのは、今まで何かそれでもすがりたいものがあったりだとか、何か今まで価値のあるものだと思っていた、だからLebenもそうですし、リスボン大震災のときには神だったかもしれませんし、そういうものを私たちは今も持っていて、大震災や大水害や、そしてパンデミックによって、ぐらぐらと揺らいでいると。今も非常に多くの、信頼すべきものががらがらと崩れているという状況がきていると思います。恐らくそれが人文科学、社会科学に従事している人間であれば、キャッチしやすいことだと思います。
それは何かというと、一つは国への不安ですよね。国というものはとっくのとうに、たとえば東日本大震災の後に信頼を失っているという人もいるでしょうけれども、それでもどこか自分たちは、最後、国が決めてくれるとか、最後、国が何かしてくれるという、そのわらをもすがる思いというのもあるかもしれません。しかし、新型コロナウイルスの蔓延に対し、政府の調整能力は明らかに欠如していると言わざるを得ない。では家族となると、家族は確かにもう濃厚接触しているわけですからとても重要な単位なのですが、しかし、その家族の中で今問題になっているのは、ヨーロッパのほうで非常に今問題になっていて、日本でもどんどん出てきている、ドメスティックバイオレンス。つまり、在宅仕事になって、特に男性が家でテレワークをするようになり、ただでさえフランスではドメスティックバイオレンスが多いのですが、そういういらいらしている人たちが次々に家族に八つ当たりをして暴力を振るうというのが急激に増えているそうです。日本でもドメスティックバイオレンスや家庭内暴力が既に増えてきていて、特に女性や子どもにとっては、家庭はコロナウイルスよりも恐ろしい空間になる。ずっと家にいますから、もし私たちが平和な家族のモデルを頭に抱きすぎていたとしたら、その私たちの希望が現実をしっかり見る目を曇らせる可能性があると思います。現在、こういうところに対するケアについて日本は遅れているし、ヨーロッパでは今本当に問題になっているという意味では、私たちはいったいどういう思考を続けていくか、深刻に問われていると思います。
そういうときには一つは希望という言葉がキーワードだと思いますが、希望的観測というものがこの新型肺炎の蔓延の中で次々に出てきていて、1、2週間後は大丈夫だろう、5月からは講義が開始されるだろうというかたちで、私たちも何となく早く終わってほしいという希望的観測を知らず知らずのうちに予測というものに置き換えてしまっている可能性があって、そう考えるとスパニッシュ・インフルエンザは非常に大きな教訓を残しています。これは何かというと、3回も波があったということです。地球を3周しています。今、マスメディアでも学者も政治家も、ピークは一度だというのをどこかで信じている節がありますが、少なくともスパニッシュ・インフルエンザ、あるいは、ペストにしてもぶり返すということはあるので。ウイルスは変異しますから、ワクチンが作られたとしても対応しきれない可能性があるということで、できる限り、ネガティブにものを冷徹に考えていく知性こそが今試されていて、何度もぶり返すよ、変異するかもしれないよ、家庭内暴力もあるよと、そういう事実から逃げない知性なのかどうか、試されています。私の周りの人文系の研究者には、膨大な事務作業に追われながらも、本当に誠実に、歴史の事実を掘り起こし、煉瓦職人のように積み上げている人たちがたくさんおられます。私は先日、岩波書店から今回のことについて書いてほしいと依頼されそのHPに「パンデミックを生きる指針」というエッセイを書き、今回もこれを一つのもとにお話しているのですが、そこでも、歴史研究仲間の優れた研究や意見などから学んだことに助けてもらいました。私は、「なんでいつもそんな暗い時代ばっかり研究するの」と言われるくらい、ずっと危機の時代の歴史研究をしてきましたが、やはりこの状況に有用な歴史的事実を静かに発信できたらと思っています。もちろん、私の研究も淘汰されるかもしれせん。そんな緊張感のなかで今研究をしています。
そして私が一番恐れているのは「複合災害」です。つまり、第一次大戦のときには戦争とインフルエンザですね。今は水害、地震という日本列島が毎年何回も直面する自然災害と、もしも今回の新型コロナウイルスが混ざったときに、もう太刀打ちできない、つまり避難所は感染源になることは間違いないので、それへの対応もどんどんしていかなければいけません。外出がかなり厳しく制限された場合、アメリカのようにホームレスを空いているホテルに収容できるかどうかも問われています。ゴミ収集の方たちの仕事はパンデミックを生き延びるために極めて重要で、しかもリスクを伴いますから、ケアが必要です。行政がなかなか想像力が働かなくて、希望的観測に曇らされて後手後手になっていると。ここは単に理系の、特にお医者さんたちの知性だけではなくて、ものを読んで書くことしかできない私たちもまた、本当に試されているなというのを強く感じますね。
出口 いろいろ重要な論点を出していただきました。パンデミックも含めた災害一般においては、最終的に弱者が一番、犠牲を強いられるということも起こるし、強者から弱者への暴力までもが発生し…
藤原 むしろ今まであったことが明らかになると。
出口 おっしゃるように、確かに、国家への信頼が失われているという事態は起こっていると思います。より一般化して言いますと、社会システムへの信頼がぐらついている、と言えるかもしれません。例えば、衛生システムや検疫・防疫のシステムといった社会システムが重層的に重なっていて、われわれは通常、その中で守られて快適な生活を送ってこられたわけですが、それがこんなにも脆いということが今回、露呈しました。当たり前だと思い、あたかも空気のように感じていた社会インフラの脆弱性に、われわれが改めて気づいたということだと思います。
もう一つ、重要な気づきとしては、近代国家が持っている国境、障壁、バウンダリーが、パンデミックにおいては意味がなかったということがあると思います。ご存知のように、昨今、アメリカ・ファーストとかブレグジットといった、いわば国家をもう一度、内に閉じようとする政治的ムーブメントが起こっていました。しかし、いかに合衆国のメキシコ国境、メキシカン・ボーダーに壁を作ったとしても、またいかにEUから離脱したとしても、ウイルスは防げないという、そういうことも、今回、あらわになったのだと言えます。国境の壁を高くすることで、労働者や移民、難民の流入は、ある程度抑えられるとしても、ウイルスの浸入は阻止できない。一国の内に目を転じても、壁や監視カメラで、金持ちが住む区画だけ囲ったとしても、やはりウイルス感染は防げない。国際政治や生活における隔離主義、南アフリカの言葉で言えばアパルトヘイトですが、そういった、一定の枠を設定して、その中だけは守ろうという姿勢では、ウイルスには対抗できないことが、誰の目にも明らかになりつつあります。加えて、これは昔から言われてきたことですが、感染症は貴賤貧富の差を問わない、王侯貴族も亡くなるし、貧乏人も亡くなるということが、今回も実際に起こっています。国境や国籍や社会階層、階級といった人間が勝手に設けている区別、バウンダリー、ボーダーを超えて、われわれは、一蓮托生というか、運命共同体なのだということに、われわれ自身が改めて気づきつつあるのではないでしょうか。

藤原 今、出口さんおっしゃったことで重要だと思ったのはボーダー、もっとわかりやすく言えば、線引きのお話ですよね。おっしゃるとおり、今、「アメリカンファースト」「ニッポンファースト」「ブレグジット」のようなかたちでの自国中心主義がずっと世界政治の中で増長してきました。イスラエルの歴史家のユヴァル・ノア・ハラリさんという方がこの前、雑誌でお書きになっていた点は、EUはチャンスだと思わなければいけないのでないか。つまり、むしろコロナ後ですよね、コロナ後にみんなが助け合わないとどうしようもないと。国境を超えて助け合わないとどうしようもないわけだから、EUの理念にもう一回戻って考え直すチャンスがきている、民主主義が今試されているということをお書きになっていました (ハラリ氏の寄稿はこちら)。ただ、それはハラリさんもおっしゃっていましたけど、一方で、それはもう一つはすごく管理的な、つまり一つ一つ人間の生体チェックを含めてビッグデータですべてを管理していくような強烈な管理主義への期待みたいなものも一方であるから、私はこの傾向をハラリさんよりも恐れています。私は第一次世界大戦の研究のあと、ヴァイマル共和国をへてナチズムへと向かうドイツ史の研究もしていまして、あのプロセスを考えると、私は現状に対してペシミスティックな気持ちに陥ります。というのは、第一次大戦後の危機に、スペイン風邪の危機、さらにインフレを経て世界恐慌といういくつかの危機の中で彼らは一貫して、非常事態的でより管理的な、ジョージ・オーウェルの『1984年』の世界のように、民間スパイを多数張り巡らせて、ドイツ民族を、そして、ドイツという国を守ろうと考えました。人々はそれを支持しました。そう考えると、今回の新型コロナウイルスの災厄は、何らかの歴史の岐路になることが想像できると思います。
先ほどおっしゃっていただいた、ボーダーの引き方ですね。もう一つ論点があります。新型コロナウイルスがこれだけ蔓延して、自分は危険だと思った気持ちというのは、実はシステムから漏れ出ている人々にとっては毎日抱く気持ちなのです。毎日新型コロナウイルスのような危険にさらされていたことに気づくわけです。私たちが依拠しているシステムが何を包摂し何を排除しているのか、歴史学でも教育学でも文学でも、人文・社会科学系の研究者は既に膨大な研究を残してきました。そういう意味では出口さんがおっしゃった、ボーダーとそれから漏れ出るものと、そして民主主義、そういうものも一から本当に再試行ですね、していくべき時代になってきているなと思いました。
疫学的思考法の重要性と危険性
出口 もう一点、最終的には今のお話にも関わっていくであろう話題を提供させていただきたいと思います。先ほど、現在のコロナ・パンデミックでは、情報はあふれているにもかかわらず、むしろ多すぎて、人々に届いていないというお話がありました。それに関連して、私が今特に感じていますのは、様々なメディアを通じて発信される専門知、この場合、疫学、エピデミオロジーという専門知と、われわれの日常的な感覚のズレです。このズレ、ないしは、われわれが、疫学的な専門知に抱く違和感が、多くの情報に接しても、それをしっくりくるような仕方で、自分のものとすることを難しくさせている一因となっており、また情報が人々に届かない背景ともなっているのではないかと考えています。こう言うと、みんなで疫学を理解し、その発想法を身につけ、合理的に行動しようという啓蒙主義的な発想と結びつきがちですが、私自身は、そのような発想法に、ある種の危険性を感じており、むしろ違和感を大切にすべきだと思っています。
そもそも疫学、エピデミオロジーという学問分野で用いられている思考様式は、徹底した統計的な思考方法だと言えます。統計的思考方法とは、一つ一つの因果関係を追跡するのは断念して、現象を徹底的に数量化した上で、その数値の間の大きな傾向性を拾い上げるというものです。個々のウイルスをリアルタイムで同定して、それに対して因果的に介入して無毒化するということが現時点ではできない以上、われわれ人類は、疫学的な思考様式に立つしかない。確かに、私もそう思います。ただ、このような発想を人の健康や命にまで及ぼして、人命を徹底的に数量化して捉えるというのは、あくまでも非常時のみに許される、やむを得ない発想法であることを、われわれとしても肝に命ずるべきだと思います。イギリスは、当初、疫学的な集団免疫という考えに立って、人口の60%、70%がウイルスにかかって、国民全体が集団免疫をつけなければ感染爆発は収束しない、従ってある程度の感染者、死者の発生は受入れざるを得ないので、過度の社会的隔離は行なわないとする、非常にハードでドライな疫学的発想に立った政策を公表しました。その後、いろいろと揺れ戻しがあるようですが、それを聞いて、私はさすがに疫学、エピデミオロジーの母国だなぁと、妙に感心しました。日本でも、疫学の専門家が盛んに各種メディアを通じて、医療崩壊をさけるためには、感染拡大のカーブを緩やかにして、重症者数を医療のキャパシティー内におさめるしかない、という発言をなさっています。それはまさにその通りだと思います。でも一方で、そこには、人の命を数量化し、大規模量として捉え、それを統計的に予測したり制御したりするという統計的発想が控えているのも確かです。そして一方、われわれが普段生きている感覚では、人の命こそ、そういった数量化ができない最たるものであって…
藤原 そういうところが研究テーマですね。
出口 ええ、特に家族であるとか友人であるとか知り合い、さらにはいわゆる有名人も含めてですが、個々の顔が見える、笑顔が思い浮かぶ人々の命、ましてや自分の命は、数量化した上で同数の他の命と置き換えることができないという、われわれが日常的に感じている命についての感覚、ひいては人間やコミュニティに対するかけがえのなさの感覚は、こういった非常時であるからこそ、大切に守って、麻痺させないようにすることが重要だと思います。現在のようなパンデミック状況では、われわれは疫学的思考様式に立たざるを得ない。これは現段階での人類の一つの限界です。この人類知の限界が、パンデミックという非常時にあって、命を数量化する「非常時の思考」として表面化している。現在、医療崩壊の現場では、トリアージという、まさに野戦病院的な対処が行われています。野戦病院というのは非常時、それも戦時の施設です。非常時の思考への違和感が消える時、われわれの思考様式のフェーズ自体も平常時的なものから非常時的なものへと、さらには場合によっては戦時的なものへと根こそぎ変わってしまう。もし、それがわれわれの間で、そして社会で定着してしまうと、あるいは、先ほどおっしゃった、ナチス的な動きが、そこから…
藤原 出てきますよね。
出口 出てくる可能性があると思います。お話にあったように、スパニッシュインフルエンザ、それから第一次大戦下で醸成された非常時思考が、その後のドイツ社会で定着してしまい、非常時体制がいわば常態化してしまったのがナチスのレジームだとすると、われわれが気をつけないといけないのは、今回もそういうことが起こり得る、でもそれは二度と繰り返してはならないということですね。
藤原 全くそのとおりだと思っています。統計は絶対に必要です。私も研究でよく用います。ただし、為政者によって曲げられない正しい統計が必要です。統計分析も必要です。ただし、偏見のない分析です。疫学も、そして医学の知識の発展に基づく的確な処置とかそういうものは絶対に必要だと思いますが、ご指摘のとおり、それは一方で、ある1人の命というものを数値化するということですから、文字どおり戦争の思考に繋がりやすい。今、私が気になっているのは、フランスの大統領のマクロンが今は戦争だと繰り返し言っていたこと。それからトランプ大統領が同じように「戦時大統領 (wartime president)」だと自分のことを言っていること。これは戦争だからしょうがないのだというかたちで人々に危険を伝え、人びとから基本的人権の抑制の同意を調達しようとしているわけですが、この言葉の中で何が失われていくのかということを私たちはこれこそ冷徹に見ていかなければいけないと思っています。第二次大戦、つまり第一次大戦から第二次大戦までを戦間期と呼びますが、その間にナチスが政権を獲得していく過程で大きかったのは、まさにおっしゃっていただいた、ヴァイマル共和国の憲法に定められた非常事態のときに大統領が緊急令を出せるといういわゆる「緊急事態条項」だったのです。それを使ってナチスは非常時だからしょうがないだろうというかたちで、報道の自由、身体の自由、表現の自由、もちろん大学の生命である学問の自由も含まれますが、そのような基本的人権をどんどん制限して他の政党を全部解体して、独裁を成り立たせたわけですが、僕が一番そのときに注意すべきだと思うのは、それに一般の人々が賛同したということですね。私たちがいいよ、ささげるよ、私たちの自由を今だったらリーダーにささげるよ、非常事態なのだからという、こういう人々のそういう、何ていいましょうか、自由を捨てる、自分の自律性を消したくなる気持ち、これと共犯関係にある中であの悲劇がなされてきたと思います。私は、本当はそこで抗うべきものこそ人文知であったり、あるいは芸術家たちが持っている感性であったりと信じています。そのためにも、独立の芸術家や研究者への支援は本当に必要です。非常事態宣言になったときには日本という社会は十八番ですが、「空気を読む」ことを強制されるわけですね。空気を読む中で異議申し立てがしづらい状況になる。先ほど私は家庭の話をしましたし、もっと小さなコミュニティの話もかかわってくると思いますけど、今は戦争なのだからという言葉はまさにキラーワードで、そういう中で、「自分はもっと休みたい」、「自分はもっと今本を読みたい」、「もっとものを考えたい」、「議論したい」というさまざまな基本的な行為が、戦争なのだからということで抑えられ、同質的な冷たい政治空間に変質してしまう。だけど、今の危機の時代だからこそ、そういう違和感とか異議申し立てをボスとかリーダーに対して自粛しない、ボスもリーダーもそれが間違っていると感じてもまずは聞いて受け止める。そういう中で上から下にという強烈なリーダーシップではなくて、ある意味状況に応じた異議申し立ての意見の交換し合いでこのパンデミックに対する危機を一つ一つクリアしていったり乗り越えていったりするというモデルも、私たちは保存しておかないといけない。普段暮らしている生活者たちのなかで、自分を大きな権力に預けたいという思いがあれだけ強くなった時代を私は知っていますから、私たちの研究は本当に試されているのでないかと思っています。
出口 わかりました。今日は、第一次大戦とリンクしつつ、その影の部分として甚大な人的被害をもたらしたスパニッシュ・インフルエンザも含め、いろいろなお話をいただきました。最後のお話を聞いて、私が思うのは、やはり「戦争」というメタファーの危険さですね。パンデミックなどの様々な災厄に対しては、「神の試練」や「人類の試練」というメタファーも使われてきました。その中にあって「戦争」という言い方は、交戦権を独占している「近代国家」という枠組みの中での発想ですね。
藤原 国だけが
出口 国だけが戦争ができる。
藤原 戦争ができ、人の命を奪い、所有権を制限し、税金を徴収し、基本的人権を制限できますね。
出口 そして、そういう発言をするのが、まさに国家元首であったり国家指導者だったりする。もう一つ、「戦争」というメタファーの危うい側面は、「勝利」という考えと結びついている点だと思います。戦争だ、だから勝とう、そしてわれわれは勝てるのだ、という発想ですね。でも相手は実は人間でもなく国家でもなく、ウイルスです。そして今ご指摘いただいたように、われわれは、最終的には、この新たなウイルスと共存していかざるを得ない。パンデミックというのは、われわれの、いわば自然誌的、ないしは生物環境的な事態であって、要するに明確な勝ち負けや、ましては勝利というのがそもそもない事柄だということが、「戦争」という言葉で打ち消されてしまう危険性があると思います。加えて、戦争の場合は、終戦日というのが何月何日と明確に言える。第一次大戦の場合は11月11日の11時ですか。
藤原 ありますよね。
出口 11が三つ並んだ時に終わったと言えて、勝った側は勝利宣言をする。恐らく今回のパンデミックも、どこかの段階で多くの国家指導者やWHOが終息宣言をするのでしょう。でも、ウイルス感染という事態は、そういった明確な終わりがない事態、このあと人類がずっと抱えていかなければならない問題なのだろうと思います。戦争メタファーは、そういった側面を覆い隠すという意味でも危険なメタファーだと思います。
藤原 コロナウイルスが鎮静化したあと穏やかな世界がやってくるというヴィジョンを、歴史研究者としての私はなかなか持てません。生活者としての私は切実に希望していますが。国の宰相も、地方自治体の首長も含めて多くの政治家がパンデミックを制圧したことを手柄として、ヒーローを気取ったりするでしょう。しかしそれよりは国家が何をしたのか、何ができて何ができなかったのか、という反省が重要です。国家は唯一、合法的に人の基本的人権や所有権を奪える組織です。その基本原理をもう一回チェックすることが重要だと思います。そして、いったい、誰の見えざる力によってこのパンデミックの危機が乗り越えられるのか、それは主にテレワークができない人びとです。つまり、医療従事者、保健所の人びと、介護士、保育士、農林漁業従事者、清掃従事者、貧困者や障害者を支えている人びと、工場労働者、接客業、郵便配達や輸送に関わる人びと、家庭の家事を担う人びと、ライフラインのメンテナンスをする人びとなどです。これまで仕事の価値の高さにもかかわらず値切りされ続け、あろうことか蔑視の眼差しさえ向けられてきた人びとが、きちんと威厳を持って生きていける社会を作ること。これは、スパニッシュ・インフルエンザのあと人類がなしえなかったことです。その事業に参画できるのか、大学の人間も試されているのです。
出口 ありがとうございます。もうだいぶん時間も経ちましたので、今日はこのあたりで終わりとさせていただきたいと思います。本当に藤原さん、どうもありがとうございました。
藤原 どうもありがとうございました。
他のレポートを読む
-
report 2021/07/30
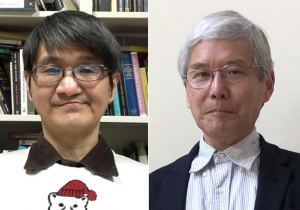
【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 科学哲学
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 仏教学・チベット学・ブータン学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 美学・芸術学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 現代社会論・社会思想 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える



 人社未来形発信ユニット基金
人社未来形発信ユニット基金