対談シリーズ「立ち止まって、考える―パンデミック状況下での人文社会科学からの発信」第4弾・前編をお送りします。今回は、こころの未来研究センター教授・内田由紀子先生と、ユニット長・出口康夫先生の対談です。これまでの対談はこちらからまとめてご覧いただけます。
この対談は2020年4月16日午前に、オンラインで行われました。
出口康夫 (人社未来形発信ユニット・ユニット長、以下出口) コロナパンデミックを受けて、京都大学の人社未来形発信ユニットが提供しております対談インタビューシリーズ、今回は第4回目ということで、社会心理学、文化心理学がご専門で京都大学こころの未来研究センターの内田由紀子さんにお越しいただいております。今回は、京都府・京都市が緊急事態宣言に準じた行動を求めているということもあり、遠隔でインタヴューを行わせていただきます。内田さん、よろしくお願いします。
内田由紀子 (こころの未来研究センター教授、以下内田) よろしくお願いします。
出口 内田さんはこの間、8か月の予定でアメリカ、カリフォルニアのスタンフォード大学に研究滞在をされていて、お子さんとともにパロアルトにお住まいだったとお聞きをしております。ところがコロナパンデミックを受けて、その滞在研究も切り上げて3月下旬に帰国なさらざるを得なかった。またカリフォルニアでは都市のロックダウンも経験され、帰国後は2週間の自宅待機もされたということですので、まずは、ご自身で直接体験された、カリフォルニアひいてはアメリカの状況と、それに対するご観察、お考えからお聞かせいただきたいと思います。
アメリカでのロックダウン
内田 実は京大の用事で2月に一時帰国をしてたんですね。そのあとアメリカに戻ったときには、日本のほうが危険性が高い状況で、アメリカは対岸の火事といいますか、遠いアジアの話だという雰囲気があったのです。私は日本からアメリカに戻ってきたということもあって、しばらく職場に来ないでほしいと言われました。
出口 アメリカでは2月の段階で、もうそういうことになっていたのですね。
内田 アジアから来る人に対する、ある種の恐怖心みたいなのが、大きかったと思います。自宅待機が解除になって、やっとオフィスに行ったら、今度はその直後ぐらいからニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスという都市部での市中感染が起こり始めました。そこからのアメリカは、感染の広がりも、またその対応も、相当速かった。スタンフォードの周りや、住んでいたパロアルト市では、そんなにリスクがあるようには感じていなかったのですが、すぐさまロックダウンになりました。あっという間に坂を転げ落ちるように、もう一瞬でリスク蔓延みたいな状態になってしまった。コロナウィルスの感染力の強さと伝播の速さもそうですし、人々の行動もそれに応じて信じられないほど素早く変えざるを得なかったということに、結構ショックを受けました。
出口 非常事態宣言が出され、都市がロックダウンされると、当然、日々の生活が激変する。すると、これはご専門の心理学に関係するかもしれませんが、人々の行動様式や、さらにいえば顔つきとか表情までが、例えばゆったりした感じのものから緊張したものへと変わってしまったという、そういったご経験もなされたでしょうか。
内田 行動や意識は、もうあっという間に変わったと思います。人との接触や、当たり前だった日常生活が急に「怖い」ものになりました。ロックダウンになるのではないかという予測が出た段階で、スーパーに行ったら長蛇の列ができていて、棚からは物がなくなっていました。そのとき人々が口にしていたのは、「ハリケーンのことを思い出す」という話でした。これは天災なのだと。ハリケーンが来る前にはたくさん買い込んで備えないといけない。ハリケーンの場合は「避難」で、今回は「閉じこもれ」と、行動は逆なのだけれども、やらなければいけないことは同じなのでないかという、ある種のハイテンションな状態でした。
メディアがあおる危機感に関しても、日本のそれと比べると、「感情を喚起する」という面が強く感じました。日本では「落ち着いて」ということが繰り返されますがアメリカではどちらかというと「落ち着くな、普段通りにするな」でした。「非常時」「戦い」「勝つぞ」という、「戦争」を認知的に思い浮かべるようなしかけとも言える「戦争メタファーの使用」が政治家やメディアから頻繁になされていたと思います。ある種そうした認知枠組みを活性化させることで、人の感情に訴えかけ、行動を変え、集団として一丸となるのだという規範行動が促されているように感じました。これは日本とは大きく異なるように思います。(アメリカでは覚醒水準が高い感情を「理想」としやすく、日本では落ち着いた感情を「理想」としているという研究が知られています(文献1, 文献2)。また、日本では東日本大震災後の報道においてもニュートラルなトーンが多く用いられていました(文献3)。)
-

ロックダウン下のパロアルト市の様子(内田先生提供) -

ロックダウン下のパロアルト市の様子(内田先生提供)
出口 今回は、お子さんとご一緒だったということで、大学の研究所以外にも、お子さんが通われていた学校のコミュニティにも属されていて、そこでは親同士のおつき合いもおありだったかと思いますが、子どもを抱えておられる方々の反応はどうだったでしょうか。
内田 子どもはアメリカの地元の地域の小学校に入っていました。シリコンバレーの地域だというのは結構大きくて、以前「技術の進歩と幸福」という論文でも紹介したのですが、学校の周りのITの環境整備というのは十全でした(文献4[PDF])。もともとこうなる前から、授業中には1人1台パソコンが貸与されて、子どもたちは普段からオンラインでの取り組みに慣れていました。ロックダウンの後はクラスの集まりもオンラインで行われ、息子の「送別会」もZoomで実施されました。学校は家にパソコンが足りない場合には貸し出しますという通知をすぐに出しました。おかげで、教育環境に関する不安感というのは日本に比べると少なかったような気がします。
出口 では大学の対応はどうだったのでしょうか。
内田 大学の対応も速かったです。スタンフォード大学には病院施設がありますのでそこの機能をいかに守るかということと、あとは学生の保護です。アメリカは学部生のうちは寮に暮らしますので、寮でルームメイトと一緒にいることでクラスターが発生することだけは食い止めねばならないという考えでした。かなり早めに授業もオンライン化してしまい、学生を寮から自宅に帰すというのが、大学が最初にやった意思決定だったと思います。
出口 私も、東海岸のハーバードでも同様の状況だと聞きました。早々に寮を閉めてしまって、学生を追い出してしまったと。追い出された学生の中には、もう故郷に帰る飛行機の便もないというケースもあって、ホームレス状態に陥ってしまった人すらいたという報道もあったとのことです。
内田 帰りにくい、帰れない人に関しては、仕方がないけれども、ともかく学生をどのように守るかということについてはすぐに決断がなされました。
出口 その点は、日本の大学、例えば京都大学と比べても、かなり対照的ですね。
内田 対照的でした。最初はあまりにもすばやい意思決定で、穿った見方をすれば、リーダーがトップダウンにその指導力や意思決定力を見せようとしているという感じもあり、「そこまでやるか」という戸惑いや批判の声が聞かれたのも確かです。しかし最終的には感染者数の増加にともない、それしかないというように受け入れられていきました。あと大学院生は、ティーチングアシスタントの仕事などでものすごく高い学費や生活費をまかなっているので、その仕事がなくなるということに対する不安についても取り除くような形での通達がすぐに出されました。これだけ「個人主義」で「自由を好む」といわれる人たちが、相当強い規制を受け入れるのを目の当たりにし、それだけ大変なウィルスであるということを再認識させられ、強い衝撃を受けました。
出口 そういう大変な状況の中で、3月下旬に帰国されたわけですが…
内田 はい。私は息子と二人でアメリカにいたので、もしも私が感染して入院隔離されるようなことになったら子どもはどうなるのだろうという不安があったのと、京大に戻ることが予定されていた6月には飛行機が飛ばなくなってしまう可能性があること、京都大学から留学している学生あてに発信された、早期帰国を検討するようにという通知も考慮し、帰国することにしました。
帰国を決めてから4日で荷物を整理し、車を売り…日々の生活や子どもの食事の用意もありましたので、本当にきつかったです。
出口 帰国後、しばらく自宅待機をされる中で、日米の違いないし落差を、いろいろとお感じになったのだろうと思います。そういった面も含め、次は日本の現状に目を転じて、どういうお考えをお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。
内田 アメリカのロックダウンの生活に慣れていたため、日本の状況が怖かったです。アメリカでは2メートルの社会的距離を保たないとといけなかった。散歩してもいいけれども、必ず人とすれ違うときには距離を取らないとならず、郵便局や銀行の窓口に行っても、お客さんは線が貼られた2メートル後ろまで下がって待って、支払いなどの操作があるときには窓口の人が十分に下がったのを確認してからカウンターに近づくというように徹底した措置が取られていました。人間の適応力というのはなかなかすごいもので、そういう行動を1、2週間やるだけでも、今度は人と安易に近づくというのが怖くなっていました。そういう状態で日本に戻ってみたら、時期的には3月後半の3連休後、東京でも感染拡大の入り口にあったころだったと思いますが、普通に人と人が近づいて話しているのを見ることになり、驚きました。特にマスクをしていない状態でも近づいていた。これが「日本は安全」というサインであればよいのですが、そうではなく「日本は安全と人々が信じているだけ」だったら、この後どういうことになるのかという危機感を持ちました。そして実際、後者のほうだったわけです。私たちの帰国時には、北米からの帰国者への待機要請が政府から出る前ではありましたが、それでも無症状で感染しているかもしれないリスクを考え、帰国後2週間は人と接触しないように買い物にも出かけませんでした。着々と感染者数が増える中、いつ日本では外出制限要請が出されるのかと状況を注視していました。
出口 一方、例えばアメリカでのマスクの着用状況はどうだったでしょうか。私も、90年代にイギリスいた時分に、日本人がマスクをしてバスに乗ったら、驚いた運転手に怒られたという話を聞いたことがありました。当時のイギリスではマスクをして外出するという慣習がなかったので。
内田 怒られるということはないのですが、奇異な目で見られるという状況だったことは確かです。病院から抜け出してきた人みたいな感じでしょうか。もともとアメリカでは、マスクしてしまって表情が見えないという状況に対する、ネガティブな感情みたいなのは結構あったと思いますね。自分が何を考えているのか、意思や表情を相手にはっきり表出することに価値をおく文化なので、マスクによって自分の表情を外に伝えられないとか、相手の表情が見えなくなってしまうということに対しては抵抗感があると思います(文献5, 文献6)。それだったら、離れてでも何となくお互いの全容が見えるほうがよいという、そういう感じがあったと思います。
それゆえかもしれませんが、マスクの効果について疑問視する報道が多く、あまり売られていませんでした。しかしロックダウンの状況下になると、郵便局や銀行に来ている人たちの間ではマスク姿がぐんと増えていました。そして今やアメリカではむしろ買い物などの外出時にマスクをかけるように義務付ける動きも出てきています。
出口 飛沫感染を防ぐという点で言うと、マスクをするか距離を取るかという二つのオプションがあって、もちろん両方やればいいのでしょうけれども、それらのうちのどちらか一方を選ぶという状況になると、文化差ないしは社会の基本的な価値観の違いが出てくるということですよね。
内田 そうですね。
日本社会の「見張り」システムの崩壊
出口 では引き続き、日本の現状についてのお考えをお聞かせ頂ければと思います。
内田 1月、2月ぐらいには、日本はすごくうまく抑え込めているというのがアメリカでもよく言われていて、「何で日本はうまくいっているのか」とよく聞かれました。そのときには日本は規範に従う社会秩序があるからではないかという解釈をしていました。つまり、アメリカのような個人主義社会では、トップダウンで厳しい制限を徹底しない限りは行動は変えられない。しかし日本のような社会ではトップダウンで命令や制限を加えなくても、お互いの社会規範で秩序を維持することができる、と。確かに日本のような社会では通常時は、お互いを「見張り」合って、ルールを破った人に対しては社会的制裁を加えることによって、トップダウンの決定機能よりも強力な仕方で人々の行動を制御して、秩序を維持している側面がありそうです。ただ、「通常時は」と言ったように、ある程度、「見張らなければならない」対象の数が少ない、小さな集団内の出来事であればそれでしのいでいける部分もあったと思います。しかし今の状況というのは、もう「見張り」システムでは追いかけられないぐらい感染者の数も増えてしまっているし、自分たちの周りだけを見てればいいという状況ではもはやない。しかも無症状で感染させてしまうこともあるかもしれないというこのウィルスの厄介な特徴のせいで、誰の行動をチェックすればいいのかもわからない。結局一人一人の行動を強く変えざるを得ないという状況なのです。そういう時に、トップダウンの意思決定が遅く、「あとは個人の判断でお願いします」というようなことではもたなくなってきています。「見張り」による互いの社会的制御が続くと、だんだん人は疲弊してきます。そうすると人は楽になりたい、そのためには「誰かが強い罰とかを与えてくれないかな」と、トップダウンの指令を待ってしまう。そういう現象が、日本の中では起こりつつあるような気がしています。けれどもそうしたトップダウンの罰に頼る選択はやや安直です。むしろやるべきなのは「通常営業ではない」システムに速やかに変えることに注力することです。例えば、はんこがないと書類の処理をしない、本人の物理的な出席がないと会議ができない、こういうシステムをまずは変えていくのが先なのです。しかし日本は全体的にこうしたことへの腰が重く、人々は疲弊し、その疲弊感から罰のシステムを要請してしまう。これは怖いことであって、本来的には自律的な組織の成員が、そのシステム変更について一人一人まじめに考えることを放棄することでもあります。こうなってしまった「組織の意思決定の重さ」のツケが後々回ってくるのではないかと心配です。
出口 私はこの間、京都にとどまっていて、犬の散歩がてら自宅近くの観光地の様子なども継続的に見てきたのですが、全国的にも指摘されているように、3月後半の3連休にはかなりの人出、特に若い人の数が多かったものの、そのあと潮が引くように観光客が減ったという印象を持ちました。つまり数日ないし1週間程度で人々の動きがかなりラジカルに変わったのを目撃したわけです。そして人々のそのような行動変容の一つのきっかけになったのは、感染の「量」に関する情報、即ち感染者数とか死亡者数やその増加スピードに関する情報というより、むしろ「質」に関する情報ではないかという感想を抱きました。例えば3月末には若者にもよく知られた有名人がコロナ感染で亡くなられるということがあり、また京都の大学でクラスターが発生して、その後2次感染、3次感染と続き、5次感染まで追跡され報道されるという事態も起こりました。そして、それらの情報がマスメディアやSNSで一斉に流れたことで、特に若者の行動パターンが急激に大きく変わったのかなと、あくまでこれは素人の観察ですが、そのような感想を抱きました。このように、個別事例ではあるけれども、具体的な名前を伴い、また身近に感じられるという意味でインパクトが大きな情報が飛び込むことで、人々の行動パターンががらりと変わるという事例はアメリカでも見られたのでしょうか。

内田 SNSにより、私たちは人との情報的つながりを手に入れることができるようになりました。このことは今回とても意義が大きいです。一つは普通だったら簡単には知ることができない他者の状況を一次情報として手に入れることができることです。それにより、私たちは具体的に自分の行動を変化させたり、他者のためになるような振る舞いを行ったりすることもできる。アメリカでもやはり有名な俳優や政財界の人の感染のニュースや、感染者や病院の現状を報告するようなSNSの書き込みは、一次情報としてかなりのインパクトをもって伝えられていたと思います。人は、「自分は大丈夫だ」という、ある種の幻想みたいなのを持って暮らしてしまうわけですが、感染についてはある意味平等に誰にでも訪れる危機である、という認識が生まれ、具体的かつ身近な事例としても感じとることができます。一方でネット上にあふれる情報は、その量ゆえに、受け取る側は質に無頓着になり、選択的に処理してしまうという欠点もあります。つまり、自分の見たい情報、自分の価値観にあう情報しか選択しないという欠点です。犯人探しのようなことが起こったり、ある特定の集団に属する人たちに対する批判が発生したりすることにもつながります。アメリカの最近のSNSの分析では、共和党支持者と民主党支持者がそれぞれの書き込みをお互いに見ないことから、情報の二極化が起こっていると指摘されていますが、これもお互いの世界観について知るための議論を遠ざける結果を招いています。
また、コロナについていえば、アメリカでは人種による感染率や重症化率の違いが取り上げられていました。それは社会システムの不平等さを描き出す啓発的価値を持つ一方で、一定の層の人たちには「自分たちは大丈夫かもしれない」という幻想を拡大させてしまうリスクもありました。同じことが日本においては貧富の問題よりも、年齢層の間の分離として起こった気がします。今回の感染症は高齢者に対するリスクであると認識してしまった若い世代の警戒心は薄く、そのために高齢層からすると若者の無頓着にみえるような行動を取り上げて、ネガティブな印象を抱いてしまうというものです。また、若者からのクラスター発生の話で言うと、その当人だけではなく関連する人々や所属集団の「評判システム」全体にかかわっているという点では、日本的な現象だと思います。アメリカでも、ビーチで騒いでいる若者たちというのは結構取り上げられていたんですよね。
出口 取り上げられていましたね、マイアミのビーチの光景とか、ドイツの若者の「コロナパーティー」なるものも。
内田 アメリカでは当人の行動に対する批判だけで収束していたようですが、日本の場合は、それが集団に帰属させられて炎上するということが起こります。一時話題になっていた「バイトテロ」みたいなもの(アルバイトの若者が働いている店舗等で悪ふざけをする動画を撮影し、ネット上に公開して炎上、その勤務先が閉鎖に追い込まれるなどした)がありましたが、これと似たようなことがコロナ感染者に対しても起こっているという印象です。集団内での責任の連鎖という考え方が強い。そうすると、集団として「絶対に感染を広げるような行動をとってはいけない」という規範が形成されます。それは日本での感染拡大を抑える一つの要素なのかもしれませんが、一方で今回のケースはバイトテロとは違い、意図的にまき散らすということでない限り、感染は悪ふざけではないわけです。感染した場合の他者からの糾弾や責任追及を恐れて、検査を受けることを回避する、あるいは症状を隠そうとするということにつながらないか、危惧しています。
出口 私の周りでも、自分が感染した場合、さらには他人にうつしてしまった場合、自分の勤めている会社、属している組織にさまざまな累が及ぶ、なので自分の行動パターン変えなければならないといった意見をよく聞きます。ここにも、今おっしゃったような日本社会の特性が鮮明にあぶり出されているということですね。
内田 自分の周辺の人たちを守りましょうというモティベーションからというよりも、もしも自分の集団内の人が感染を拡大させたら評判やメンツにもかかわるのだから、組織として集団成員の行動の自粛を促したり、組織のシステムを変えたりしようとするということはよくあると思います。逆に言うとそういうモティベーションでもない限り、日本の組織がシステムを変えるのは難しいのかもしれません。ただ、先ほども述べたように、こうした集団監視的なことが強い糾弾などにつながってしまうと、今度は個人が本当のことを伝えられなくなって、かえって集団にとってよくない結果をもたらします。誰かを強く批判する傾向はネット上ではよく見られますし、正義感で書き込む人もいるのだとは思いますが、そのことがもたらすネガティブな効果にも、正義感がある人にこそ、気が付いていただければと思います。
出口 そのとおりですね。上からの同調圧力とはまた異なった、横からの同調圧力というのがあって、これがきつすぎると、集団の中での逃げ場がなくなり、それに少しでも違和感を抱いた個人は、本当に追いつめられてしまうことになる。
内田 どうしてもこういう状況下では同調圧力が高まるので、その効用と負の側面についてはよく考えたほうがよいですね。
出口 コロナパンデミックにまつわって飛び交っている情報について、もう一つ論点を出させていただきたいと思います。今回のパンデミックをめぐる情報環境の特徴は、スマートフォン端末と結びついたSNSの普及にあろうかと思います。SARSやMERSの流行時に比べても、コロナパンデミックをめぐってSNS上で飛び交う情報量は圧倒的に大きいのではないか。またより重要なことに、多くの人々がマスメディアよりも、むしろTwitterやFacebookで流れる情報のほうに注意を向けていて、大手メディアの報道よりも、SNS上のネットワークで流れている情報の方を信頼しているのではないか。その中で「インフォデミック」と言われる、情報のオーバーフローや、デマの発生ということも起こり、またバッシングや炎上という事態も多発しています。一方、インフォデミックの中にあっても、流言飛語にうかつに乗らず、飛び交う様々な情報を注意深く吟味する、メディアリテラシーを備えた層も確実に厚みを増しているとも感じますが。
内田 こうした恐怖心が高まる状況では、誰もが何らかの一次情報を知りたいと思うものです。例えば実際に感染してしまった人や回復した人はどういう経過をたどったのか、などです。これはコロナに限らず、身体的に気になる症状があるときにネットで検索をし、重い病気かもしれないと思って思い悩む人が結構多くいると聞いたことがあります。生の情報に触れること、触れられることは大切でもあるのです。それによって私たちは他者に対する共感や思いやりを持ち、協力行動をとることもできるかもしれないのです。もちろん、その際には木を見て森を見ないということにならないようにしないといけない。つまり一つ一つの情報はどれだけ典型例であるのか、確からしさなども含めた全体を俯瞰する力も重要になってきます。
「集合活動」のメリットとめんどくささ
出口 ありがとうございます。これまでは、アメリカとの比較も含めて日本の現状についてのお話をいただきました。次は、そこから見えてくる日本の課題、日本社会の問題点についてのお考えをお聞きしたいと思います。
内田 システムの変えられなさ、組織の意思決定の重さというのは、日本が今抱えている課題です。アメリカにいたとき、先ほども申し上げたのですが、あっという間にいろいろなことが変わったのですよね。それはもう、びっくりするぐらい速かったです。あれだけ個人の行動の自由を大事にしている社会が、あれほどあっという間に行動を変えざるを得なかった。しかも相当トップダウンだった。それを目の当たりにしたあとだと、日本はなかなかシステムが変えにくい社会なのだなと思いました。「変える」「影響を与える」ということについて、ある種の自己規制がかかりがちです。日本ではどちらかというと人に影響を与えることよりも、周囲の状況にあわせて「調整」することのほうが得意で、よく用いられる行動方略です(文献7)。思い切って一番乗りに「変えます」という時には組織の腰は重く、周りが変わり始めることでようやく、その流れに「あわせて」自分たちの状況を調整する、となる。そうするとある一定以上の変化に至るまでの初動がすごく遅くなるのです。例えば大学でも、いろいろな書類はそのままハードコピーで出さないといけないとか、意思決定をするようなミーティングは直接対面しないといけないとか、そうしたことが修正されるのはアメリカのように「あっという間」というわけにはいかないことでしょう。
出口 いまだに、はんこを押さないと書類が回らないという。
内田 そうです、そうです。はんこを押さないといけないところはまだまだ多いのではないでしょうか
出口 はんこを押すためだけに、命懸けで出勤しているという話も聞きますが。
内田 そうですよね。それはニューヨーク・タイムズでも先日記事になっていました。日本はこれだけ先進国なのに、アナログなはんことかファクスに依存していますみたいな話でした。日本の仕事の仕方は「集合活動」なのだと思います。これは私のチームの研究結果ですが、日本社会の協調性というか互いの評価を気にする傾向は、農業地域で高いのですが、その理由の一つは、集まって活動する機会や参加率の高さにありました(文献8)。水田農業では用水路の設備なども含め、いろいろな人の力と協力が必要です。そうして共同で働く中で、お互いを気にかけ、ケアすることを通じて、少し面倒なことがあっても健康につながるような社会関係を維持していたのですね。会社の組織でも似たようなことがあります。オフィスのレイアウトは「島」になっているところも多く、その「島」の中での情報共有や集合的な寄り合いを通じて、評価が行われたり、会社の重要な決定がなされたりということがあるようです。職場における協調性から身体的なメリットが生じているという知見も得られました(文献9)。それが無くなってしまうと、互いの働きについての評価を「成果物」をもとにするしかなくなる。果たしてそういう仕組みに思い切ってシフトすることができるかどうかです。今までの規律と全然違う評価指標をもって評価をし、管理、監督するということに対応していかないといけない。
出口 日本社会が、政治的な介入などのトップダウンによってではなくて、むしろ社会内部のコンベンションないしは横からの同調圧力で動いている社会であることのいい面、悪い面の両面がいま、改めて顕在化しているということですね。
内田 そうですね。日本では、自分たちがお互いに直にコミュニケーションをとったり、働きぶりを見たり、あるいは何を考えているのかを探るということに依存して、意思決定のシステムを作り上げてきたと思うのです。それを現状のオンラインのミーティングなどで代理できる部分があるのか、代理できないとしたらそれをどのように解消するべきかなど、懸念があるのだと思います。集団で集まっていろいろやることには良い面も悪い面もあって、みんなで集まって何かやることで得られる楽しみが幸福でもあるし、それが日本社会の、ある種の面倒くささとかしんどさでもあった。面倒なことをやることによって、ある種保険をかけているというか、ケアもしてもらっているという部分があった。集合活動から得てきたメリットが多かった人ほど、これからの状況は徐々に大変になってくると思います。逆に面倒さのほうが勝っていた人にとっては、楽になっている部分もあるかもしれませんが、気が付かないうちに集合活動の恩恵を受けていたということもあり得ます。これから日本社会の中でどのように幸福や安寧を求めたらいいのかとか、心身の健康を担保するにはどうすればよいのかということを今のうちに真剣に考えておく必要があります。
(以下、後編に続きます。)
他のレポートを読む
-
report 2021/07/30
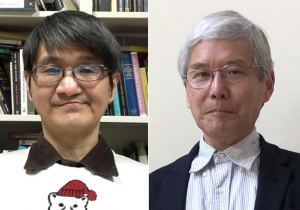
【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 科学哲学
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 仏教学・チベット学・ブータン学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 美学・芸術学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 現代社会論・社会思想 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える



 人社未来形発信ユニット基金
人社未来形発信ユニット基金