対談シリーズ「立ち止まって、考える―パンデミック状況下での人文社会科学からの発信」第2弾・後編をお送りします。前回に引き続き、本学文学研究科名誉教授で現在、京都産業大学客員教授の伊藤公雄先生と、ユニット長・出口康夫先生の対談です。本対談の前編はこちらからお読みいただけます。
なお、この対談は2020年4月3日に行われました。
「ショック・ドクトリン」に抗して
出口康夫 (人社未来形発信ユニット・ユニット長、以下出口) 一般に、ウイルスに対抗するために生物が取るべき一つの進化論的な戦略としては「分散」が考えられますよね。みんなが一箇所に集中しすぎた場合、そこで感染症が蔓延すると、種全体が絶滅してしまう危険性が高い。だから、感染症による絶滅のリスクを下げるためには、個体同士ないし小集団同士が適度に分散して、その間を緩いネットワークで繋いでおくのがベストだという…
伊藤公雄 (本学文学研究科名誉教授、以下伊藤) 棲み分け理論の梅棹史観みたいなものですね(笑)。
出口 私としては、今後、このような考えを人間の社会に適用する発想が、良いか悪いかは別にして、より前面に出てくる可能性があるのではないかと思っています。既に、国際社会のレベルでは、アメリカ・ファーストとかブレクジットといった、ある種の孤立主義の流れが見られます。一方、一国の内部に目をやると、単に地方自治体の権限という政治的・統治機構的な側面だけでなく、社会の在り方全般を、より自律分散型にしていこうという流れ、現在の首都圏への過度の一極集中を見直そうという動きも出てくるのではと、これは期待も込めて、そう考えているのですが。
伊藤 ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』ではないけども、危機的な状況というのは、大きなパラダイムシフトが起こるときですよね。さまざまなものが生まれる契機でもある。社会的危機状況で、僕が最初に「あれ、変化したな」と感じたのは、阪神・淡路大震災の95年のときでした。メディアの描き方に変化が生まれた、という文章を産経新聞に書いたことがある。つまり、記者たちのまなざしがあの時変化したと思った。彼ら彼女らが現場に入ったときに、自分たちも被災者だという、被災者の目線で記事を書くという動きが生まれた。あるいはテレビカメラも、客観的にその被災を映すのでなくて、被災者の側に立った映像を作るという動きがあった。「ただ外側から眺めて報道するだけだった日本のメディアが変わる契機になるのではないか」と書いた。でも、やはり1週間でこうした動きは消えていった。
次に考えたのは、東日本大震災のとき。震災直後に、東京で東北大学の友達と一緒になったとき、彼が、「阪神・淡路のときにはボランティアという新しい動きができた」と言い始めた。ボランティアは、確かに95年の一つの成果ではあると思う。『ショック・ドクトリン』のある意味逆をいった、プラスの社会的な産物だろうと僕も思う。彼に「阪神淡路大震災では、このボランティアという言葉がキーワードになった。東日本では何ていう言葉がキーワードになるのかな?」って言われたとき、僕はとっさに「デモクラシーじゃないか」って言った。あのときに、2万人近い人が津波で亡くなって、たくさんの被災者が出た。でも、そうした被害のなかから、いろいろな新しい動きが草の根で始まった。地域だったり、共同体だったり、一人一人が自分で決めながら身の回りの仕組みを動かすという動きが可視化し始めた。日本の戦後社会で、実は成熟しきれなかった下からのデモクラシーみたいなものの芽生えがみえてきたのではないか、と思ったわけ。もし、この動きが広がったら、日本の社会がプラスの方向に変わるきっかけになるのでないかと思った。実際に、あの危機的状況のなかで、下からのデモクラシーは一時的には機能したと思っています。でも、半年もたないくらいのうちに、結局、政府の管理下で、「復興」という名前のもとで、お金の問題も含めて、さまざまなものが再びコントロールされてしまった。こちらはまさにナオミ・クライン流の、「危機便乗型経済」、「危機便乗型資本主義」だったわけです。
今回も、同様の動きが絶対出てくると思います。こうした危機便乗型の「お金儲け」に対抗する、「危機対応型デモクラシー」とか、「危機対応型資本主義批判」とでもいえるような動きを生み出す必要がある。そうしないと、結局、危機便乗型の資本主義や、危機便乗型の統制国家に、すべてすくい取られてしまうのでないかと思う。その辺のところは、かなりわれわれは冷静に考えておく必要がある。危機ではあるが、この危機をどっちの方向に動かすかが問題です。現在のアベノミクスに見られるような、ある種格差を拡大するような経済政策、生産性優先、利益優先の仕組みを維持するのか。それとも、現状の大企業優先型の仕組みをひっくり返すような、経済の仕組みの転換を求める批判的動きのきっかけにするのか。また、危機に便乗して統制型の国家が生まれようとしているときに、これを契機に、対抗的なデモクラシーみたいなものを作り出すのか。

そのとき、地方自治体というのは一つの窓口なのかなと思う。もちろん、もっと小さな共同体や組織も含めて、ラディカルな形でデモクラシーを再生することが問われてくると思います。まさに東日本大震災のときに芽生えた新しい草の根のデモクラシーを、これを機会に自分たちで作っていく。そうしていかないと、経済もこれから悪化するのは明らかです。だからこそ、他者と助け合いながら、自分たちで決めながら生きていくための場所と関係性を生み出していく必要がある。残念ながら、今は資本主義の枠の中でしかわれわれは生きられないわけだけど、自己増殖のみを求める資本の論理の自動展開に対して、それを批判し、制御するための仕組みを、下から作りださなければならないと思う。いわば市場経済の仕組みとやり取りしながら、自分たちなりの自立したスペースみたいなもの、デモクラシーに依拠した関係性を作っていけるかという問いが多分、近々求められる。その準備を人文社会学者はしなければいけないのでないかと思いますけどね。
ソフト・インフラの予防的整備
出口 いま、大震災後、戦後、未完のままだったデモクラシーが再起動される可能性が芽生えたにもかかわらず、それが再び未完のままに留まってしまっているというお話がありました。それとパラレルな動きだと思うのですが、大震災からの復興の過程で、津波を防げなかった堤防とか、津波で破壊された都市基盤といったハードなインフラを、以前より強力に再建しようとする「国土強靭化」という大きな流れが出てきました。ここで問題なのは、制度面・ソフト面にわたる、地域に根ざした民主化の動きが、結果として、そのハード面での強靭化の流れの中でかき消されてしまったことだと思います。一方コロナパンデミックの場合、例えばイタリアで現に起こっている医療崩壊や、日本でも起こり始めている外食産業の崩壊といった事態は、ソフト面で社会を支えるインフラの危機だと言えると思います。震災時と異なり今回のパンデミックでは、このソフトな社会インフラの脆弱性が、あちこちで露呈しているわけですが、ここでも同様に、ソフト・インフラの構造的な問題点がそのまま放置され、何らかの仕方でハード面での復興に回収されてしまうのではないかという危惧を抱いています。
伊藤 強靱化路線は、結局、公共事業が減って経営が苦しくなった土建屋さん向けですね(笑)。いわゆるゼネコンの人たちにお金を回すための政策ではあるわけです。ただ、今の日本には強靱化が必要な部分もある。1970年代ぐらいに作られたコンクリートの建物とか橋とかトンネルとか、すごく危機的な状態にきている。それをきちんと見直して、補強するようなことは重要だと思っています。ゼネコンにお金を回すために作りすぎてしまった部分もいっぱいあるけど、きちんと見直しながら、必要なものを整備することは重要です。橋とかトンネルとかいうのは今けっこうあぶない状況になっている。そこにお金をかける。必要な補強のためにお金をかけるという強靭化は必要ではないかと思う。もちろん、これ以上、不必要に新しいもの作る必要はないと思います。
一方で、おっしゃるようにソフト面も重要です。特に社会保障面は、高齢社会の進行のなかで大きな課題です。財政難と言いながら切り捨ててきた部分をどうやって立て直すのか。こうした状況であるにもかかわらず、東京都は都立病院を民営化するようなことを決めているわけです。本当に矛盾している。このままいくと、日本の医療崩壊があらわになっていく可能性もある。それをきっかけに、おっしゃるような医療の再建、あるいは社会福祉の再建をするということは、今からもう考えてかなければいけないことだと思います。
日本の場合、医療問題はたくさん課題をかかえているのですが、何よりもお医者さんが少ない。僕も入院したことあるけど、大体、お医者さん、特に勤務医の人たちはみんな目が真っ赤です。72時間連続労働みたいなことをやっている人がいっぱいいる。なぜかというと、医療費の配分の問題がある。日本の医療費ってその多くの部分が薬と医療器具に回っていますよね。人件費は削られて、そのぶん薬と医療器具に向けられている。今回、日本はCTもMRIも充実していると言われていますが、たしかにそのとおりなんです。世界でこんなに高度の医療器具持っている国もないといわれている。ただ、何でそうなるかといえば、薬と医療器具にばかり医療費使っているからですよ。ほかの国は、日本ほど高度な医療器具は行き渡っていない。日本の場合、今回多分あらわになるのは、お医者さん、看護師さん、検査技師の人も含めてですが、医療従事者の体制が実はすごく不十分だということだと思う。もしこのままイタリアのようになっていったら、イタリアより悲惨な状況になりかねない。今だって連続72時間労働みたいな人たちが大量にいる状況で、イタリアなみに感染者が出たときには、医療従事者はどんどん死んでいくような状況になりかねない。
出口 さらに地震とのアナロジーを続けます。地震対策の場合、特に日本は一時期、地震予知に力を注ぎ、地震被害を、いわば水際で食い止めるという戦略を取っていたわけですが、最終的には、それを放棄せざるを得なくなりました。予知は断念して、「防災」よりはむしろ「減災」、即ち、予知できないまま地震に見舞われても、その被害を減らせるように、予防的に社会の備えを強化しておくという戦略に転換したわけです。先ほど触れた「国土強靭化」には、そのような側面もあったことは確かだと思います。同様の発想の転換が、感染症の予防にも求められているのではないでしょうか。今回のコロナパンデミックでは、台湾など少数のケースを除いては、感染を水際で防ぐことに成功した国はほとんどない。先ほど「最初から負け戦」というお話がありましたが、気が付いた時は、既にウイルスが国内に蔓延していたという事例がほとんどでした。今回の教訓を生かすためには、医療制度・保険制度はもとより、感染が拡大すれば崩壊する様々なソフト・インフラを、特に人的な手当てといった側面を重視しつつ、予め、パンデミックが発生した場合を想定して、普段から守っておくような制度設計が必要ではないでしょうか。例えば、ソフト・インフラに様々な冗長性を持たせておくことで、パンデミックへの頑健性や、そこからのレジリエンスを普段から確保しておくかという「守り」の姿勢、「減災」的な視点を持つことが重要だと思います。そのためのコストを、社会全体で、それも一国に止まらず、国際社会全体で負担し分担するというシステムづくりが求められているのではないでしょうか。

ケア・ヴァルネラビリティ・弱さの思想
伊藤 僕はジェンダー論とか男性性研究をやっているのですが、今、ジェンダーや男性性をめぐる領域でもケアの倫理みたいな議論が起こっている。ここで言うケアは、他者の生命や身体や、さらに言ったら、他者の思いまで含めて、配慮しながら対応していくという力だと思います。そうしたケアの力が問われている。他者への配慮だけでなく、自分に対するケアも必要です。特に、男性文化は、他者へのケアも、また自分自身の生命や身体への配慮の力も弱い。今、そうした自他に対するケアの視点みたいなものが問われている。ケアの倫理が機能していれば、医療崩壊にはならないわけです。逆に、日本の現在は、ケアの倫理をないがしろにしてきた。他者に対する配慮もしないし、自分に対する配慮もしない。男性主導のマッチョな文化の持続のなかで、ケアの能力を欠いたまま、今、コロナウイルス対策をし始めている。それはすごく危険な状況だと思う。だから、妙な決断主義が出てきたり、「戦争だ」みたいな発言が生まれる。どうやって他者にケアの視線を向け、共存していくための仕組みをどうやって作ってくのかが問われているのに。
例えば、今、熱が出たらどうしますか。高熱が出たら医者に行っても「来院してもらったら困ります」って言われますよ。特に大病院は「院内感染が起こる可能性があるから来るな」になっている。「コロナの検査してもらえます?」と言ったら、できませんとなる。どこに行ったらいい? もう本当に、社会的に人をケアする仕組みそのものが崩壊してしまっているわけです。ケアという視座から、感染者の身体や生命に配慮したら、こんなことにはならない。こうならないように、さまざまな工夫が政府に求められているのに、そうした対応がまったくとれていない。人間の生命への視点が欠落しているとしか思えないような対応です。だからこそ、ケア、特に男性たちが見失っているケアの力の再生という視点から、もう一遍社会を再生していくようなことが必要です。ケアの力の重要性は、今の状況だからこそ問われている。現在の日本の政府が完璧に欠落させているのは、そういう一人一人の思いとか、身体とか生命に対するケアの目線、ケアの視線だと思う。そうしたまなざしが欠けているから、今のような不安定な状態になってしまっている。「マスクで自分を守れ」みたいな話になってしまっているわけです。ケアという観点から、社会を再編成していくための基本的な理念の組み換えも、今後、改めて求められているのだろうと思いますよね。
出口 さらに言うと、他者に対するケアの基礎は、自他のバルネラビリティ(vulnerability)、すなわち脆弱性・弱さ・傷つきやすさの自覚にあると思います。「バルネラビリティ」は20世紀後半の哲学の一つのキーワードにもなった言葉です。私は傷つきやすい、同様に他人もまた傷つきやすいということに本当に気づいたとき、われわれの他者に対する態度は大きく変わることになります。ここで言うバルネラビリティとは、単に「壊れやすい」という意味ではありません。壊れると言えば、コンクリートの堤防でも、場合によっては津波によって壊れてしまいます。バルネラビリティ・傷つきやすさには、傷ついた場合の痛みの感覚、痛みには身体的な痛みと心理的な痛みの両方がありますが、その痛切な痛み、そしてそれを恐れる、これまた切実な感情がつきまとっています。コンクリートと異なり、われわれは自分が壊れやすい、傷つきやすいことを知ってしまっていて、傷つくことをつねに恐れて、心のどこかでビクビクしながら暮らしているのです。人間が傷つきやすいということは、その人間が作っている社会も傷つきやすいことを意味します。人間や社会のバルネラビリティの自覚があってはじめて、ケアを人間関係の基軸にすえるという考えが出てくるのです。
伊藤 ケアの話って同時に「弱さの思想」の問題でもある。他者性の問題ともからむ、他者と共存する力の問題でもあるわけですよね。ところが、今の日本の政治体制というか社会の仕組みも含めて、他者との共存の仕組みというのはものすごく弱くなってしまっていて、自分を防衛できればいいという仕組みでもう、総理大臣自身が自分と自分の身の回りの防衛のために、「やってる感」だけでずっと動いてきたわけだから(笑)。
ケアの力の形成とともに、他者と共存していくような仕組みを作っていかなければいけない。今回の新型コロナ感染を、そうした新しい仕組み作りの契機にしていくことが重要です。そのためにも、開放されたコミュニケーションの回路の形成という課題がさらに加わる。「弱さの思想」、ケア、コミュニケーション、このあたりが、今後のキーワードになってくるのかもしれないと思う。
出口 ここで、最初のイタリアの話に戻りたいと思います。イタリアでこれだけの感染爆発が起こってしまっている背景には、すごく親密でインティメートな人間関係、いわば「密閉」「密集」「密接」の「三密」の見本のような文化や社会のあり方もあるというお話でした。そのイタリア社会の「三密」的なあり方、「三密性」が、今回は、ウイルス感染に対する弱さ、脆弱性として現れてしまっているわけですが、逆にそこにこそ、イタリア社会が秘めている強さ、パンデミックからの復元力の鍵が見出せる。バルネラビリティのコアは、実は身体性です。傷つき、血を流し、痛むのは、まさに身体です。人は身体を持っているからこそ、さらに言えば、身体と不可分な存在であるからこそ、傷つきやすい、バルネラブルな存在なのです。そういった人の身体性に根ざしたバルネラビリティに対する直感を、イタリアの人々は、どこかで豊富に持っていて、互いの弱さ、傷つきやすさを、抱擁やキスによって、体温を伝えあい、文字通り温めあうことで、身体的に補い、乗り越えようとしてきた。そして、そこにこそイタリアの未来がある。それに比べて日本は、どこか冷たいというか…
伊藤 イタリアの思想家ヴァッティモたちのいう、強固な主体に裏付けられた強くて硬い思想に対する「弱い思考」が、20世紀のイタリアではすでに生まれていました。ここには、バルネラビリティとも関係する視座がある。ヴァルネラビリティと重なるけど、「弱さの思想」とでもいえる視点はすごく重要だと思う。逆に、現在の日本社会は、マッチョな「強さの思想」にとらわれすぎているようにも見える。伝統的な日本文化には「弱さ」「はかなさ」への視点がすごく重要だったのに。日本の文化には、もともとイタリア以上に、そうした「弱さ」への観点があったはずなのにね。バルネラビリティをある種重視するというか、そういうカルチャーがあったはずです。それが戦後の経済成長の中で、むしろ反対の攻めの思想とか、強さの思想みたいなところに傾きすぎてきたのではないか。ただ、潜在的に日本にある弱さの思想みたいなものと向き合うというのも、さきほどのケアの話とか、他者性の話も含めてですが、これからすごく重要になってくる部分だろうなとは思っています。イタリアの場合、これは先ほども言ったけど、高層マンションで、みんなで6時に窓を開けて(笑)
出口 歌を歌う。
伊藤 歌を歌う。一人ではさみしいから(笑)。とにかくみんなと一緒にいたいという、ある種の親密な共同性みたいなものを、求めている。それは逆に言ったら自分たちの弱さみたいなものを共有しているということかもしれない。
出口 さらけ出すということですよね。
伊藤 まさにそういうカルチャーが、イタリアの場合あるのだろうなと思います。
出口 繰り返しになりますが、それが今回のイタリアの感染爆発の背景にあるのかもしれないけれども、逆に互いに弱さをさらけ出すという文化が、社会が復元していくための、そのレジリエンスの源泉になると。
伊藤 そうあってほしいし、多分そうなっていくのだろうと思いますね。これだけ社会が傷ついてしまったときに、社会を再生していく中で新しい関係性みたいなものが作られていく必要がある。もちろん、それは伝統的な文化的な社会的歴史的背景をもとにしながらだとは思います。危機の時代だからこそ、そうした次の時代へ向かう新しい動きが出てくることを期待したいし、僕はそうであることを信じています。
出口 わかりました。今日はどうもありがとうございました。
他のレポートを読む
-
report 2021/07/30
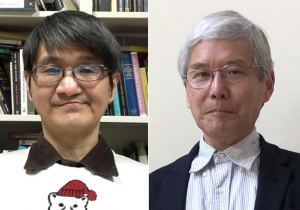
【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 科学哲学
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 仏教学・チベット学・ブータン学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 美学・芸術学 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える -
report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 現代社会論・社会思想 #こころの未来研究センター
立ち止まって、考える



 人社未来形発信ユニット基金
人社未来形発信ユニット基金